いわゆる“確証バイアス”と呼ばれるものがあります。
自分が欲しい情報等を選択的に取り入れ、意思決定を誤らせてしまう、一般的にはネガティブに語られるものですが、実は意外にも学習において重要な役割を果たしています。
ここでは自主的に学習する事の重要性と確証バイアスの関係性について見ていきます。
選択の自由は学習効率をあげる
バイアスと学習の効率について調べた、興味深い研究があります。
研究の内容は次のようなものです。
- 参加者に対して2つのシンボル画像を見せ、どちらの画像がより多くのポイントを獲得できるのかを、試行錯誤しながら学習した
- ポイントはお金に換金できる
- ポイントが増える「報酬」のシンボルの方が、ポイントが減る「罰」のシンボルよりも早く学習することができた
- シンボル画像の選択後に結果がわかる実験においては、選択したシンボルの「報酬」が多い場合と、選択しなかったシンボルがポイントが減点される「罰」の場合に、学習効果が高かった
ここまでの内容で言えることとして、「罰」よりも「報酬」の方が、学習効果が高いという点が一つ。
加えて、「報酬」の存在のみならず「罰」の存在からも高い学習ができる、という点です。
重要なのはここからです。
- 参加者に対して選択肢を指示する「強制」の実験も行われた
- 参加者は「強制」された選択肢を選んだ場合、「報酬」による学習も「罰」による学習も、同程度の学習効果、つまり学習効果が悪化した
- 研究者は、自由な選択を行った場合、「確証バイアス」が働き一定の学習効果の向上が見られたが、選択肢を奪った強制環境においてはこの「確証バイアス」が消失した、としている
つまり、自主的に学習するのか、学習を強制されるのかで学習効果が異なる、ということです。
この知見を活かすには?
研修において、自主性の尊重を設計に組み込む
この知見を現実のビジネスや生活に活かすにはどうすれば良いでしょうか?
1つは、会社組織における研修への活用が考えられます。
一般的にビジネスの研修は、カリキュラムもコンテンツも決まっており、従業員に対して「強制」を行うものです。
「強制」の学習効率が悪いのは上述のとおりです。
会社としては、これこれを勉強して欲しい、という内容は当然にあるでしょう。
しかし、自由度を高めることはできるはずです。
例えば、オンライン教育に切り替え、学ぶ場所や時間を自由にさせる。
一定の学習範囲の中で“必要単位”を設定し、“単位履修”をすれば研修OKとする。
というようなものです。
つまり、自主性の尊重を研修の設計に組み込む、ということですね。
思考の偏りについて、それを正す“自由”が自分自身にあると思う
次に、自分自身の思考の偏りについて正すこともできると考えられます。
人間は一般的に、他人に間違いを指摘されると不愉快な気持ちになり、意固地になり、仮に本当に間違えていたとしてもそれを受け入れ改善につなげるのは容易ではありません。
しかし、自分自身で自分自身を正すのであれば、その不愉快さは軽減されるはずです。
ようは、自分自身を正す“自由”が存在する、ということです。
自分自身が考えていることについて、あえての反論(デビルズアドボケイト)を行ってみると良いかもしれません。
(この点については、上述の実験において研究者も一部指摘をしています。より正確には、陰謀論等にハマる人も、確証バイアスにより学習が強化されている、という指摘ですが。)
コントロール感の存在も重要か?
懸念としては、単純に自由度がある、自主的に取り組めば学習効果が高くなるかどうかは不明だ、という点です。
別の研究では、仮に自由度が高い、自主的に取り組める環境であったとしても、組織の上の立場なのか、それとも下の立場で学習効果が異なることが指摘されています。
(上の立場の方が、自主的に取り組んだ際の学習効果が高い。)
もしかしたら、“コントロール感”の重要性が大きいのかもしれません。
となると、単純な“自由度”という観点ではなく、“コントロール感”という観点で物事を設計していく方が正しいかもしれません。

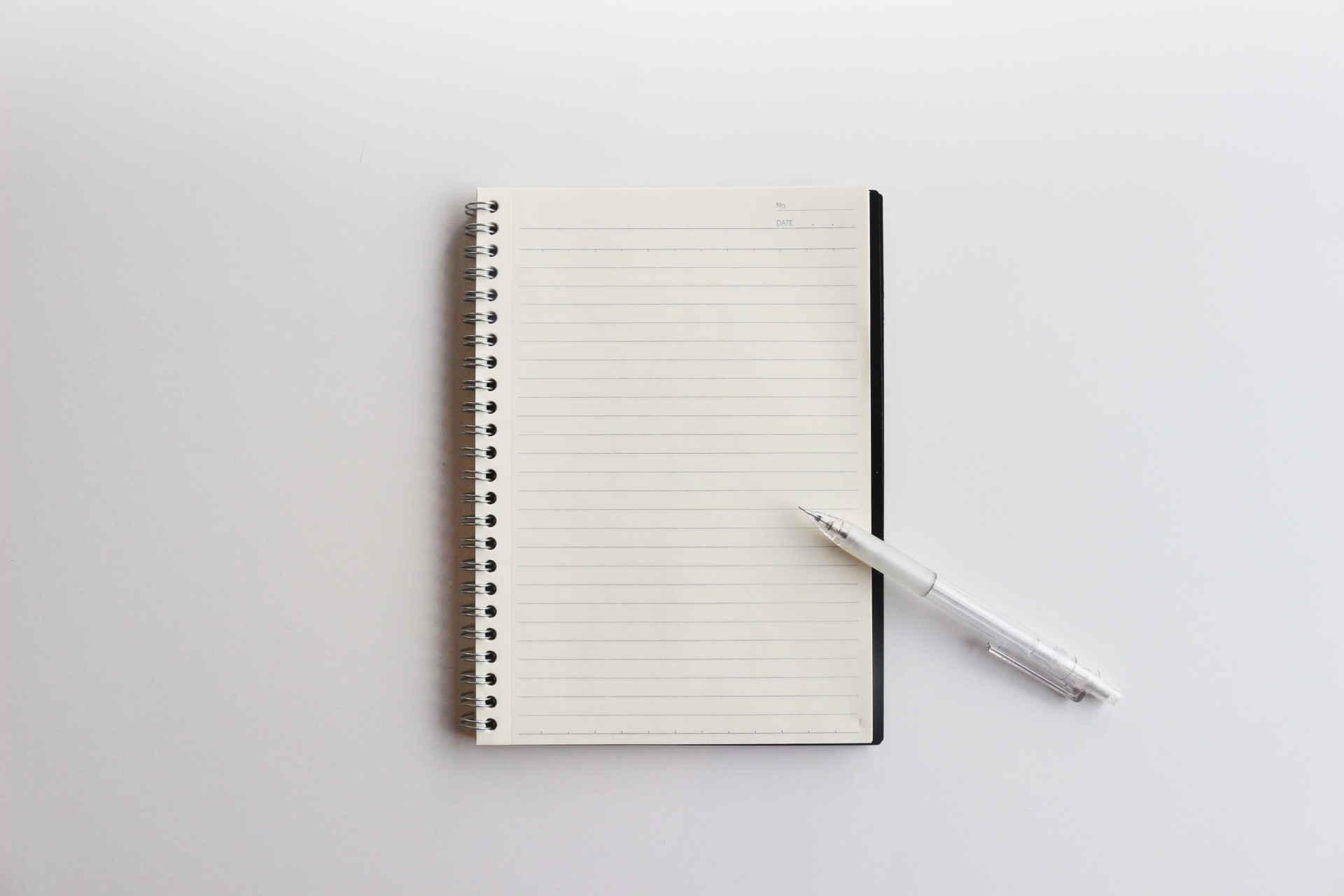

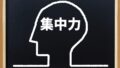

コメント